コミュニティ・スクール
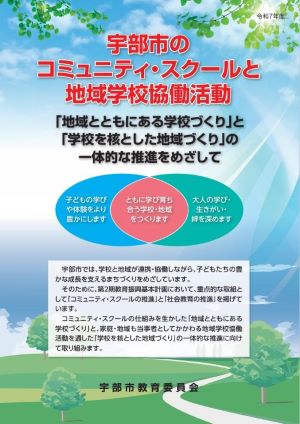
宇部市では、学校と地域が連携、協働しながら子どもたちの豊かな成長を支えるまちづくりをめざしています。
そのために、「第2期教育振興基本計画」において、重点的取組として「社会教育の推進」と「コミュニティ・スクールの推進」を掲げ、「地域とともにある学校づくり」と家庭・地域も当事者として子どもの教育にかかわる地域学校協働活動を通した「学校を核とした地域づくり」を一体的に進めていきます。
国・県のページ
- CSハンドブック~学校運営協議会の更なる活性化をめざして~ 山口県教委(外部リンク)

- コミュニティ・スクールの在り方等に関する検討会議 最終まとめ(文科省)(外部リンク)

- 地域学校協働活動の推進に向けたガイドライン(文科省)(外部リンク)

- 人口減少時代の新しい地域づくりに向けた社会教育の振興方策について(答申)(文科省)(外部リンク)

- 今後の生涯学習・社会教育の振興方策について(R5.3.8)中教審生涯学習分科会(外部リンク)

- 教師を取り巻く環境整備について緊急的に取り組むべき施策(提言)中教審(外部リンク)

- 次期教育振興基本計画について(答申)中教審(外部リンク)

コミュニティ・スクールの取組
コミスクホットニュース
12月18日(木曜日) 地域の方も参加~歌人岡野大嗣先生による短歌教室
岬小学校

岬小学校では、昨年度に引き続き今年度も、歌人の岡野大嗣(だいじ)先生にご来校いただき、6年生を対象に短歌教室を開催しました。今回は、岬ふれあいセンターからの呼びかけで、短歌に興味・関心のある地域の方にも参加していただき、子どもたちと一緒に短歌づくりを体験されました。地域の方は、「子どもの豊かな発想や感性は素晴らしい」と、とても感心されていました。
岡野先生は児童一人ひとりに短歌づくりのアドバイスを行い、「歌を作っているうちに何かに気づくという、短歌の一番楽しい部分を感じてほしい」とみんなに話されました。
また、授業後には、5年生以下の児童も、自分の作品を添削もらいたいと岡野先生を囲んでいました。
この短歌教室は、岬小の児童が岡野先生にファンレターを送ったことがきっかけで実現したものです。昨年度の短歌教室以降、岬小には児童有志による短歌クラブも結成され、短歌づくりに親しんでおり、中には短歌コンクールに応募するほどの腕前となり、入選した児童も出ています。
子どもも大人も一緒に学び合うこの短歌教室が、岬小と地域の特色ある取組として今後も継続されることを期待しています。
特色ある学校の取組
学校の特色ある取組を紹介しています。

-
R7.11.27 厚南中学校 拡大きれいにしちゃいたい (PDF 254.0KB)

-
R7.10.30 西宇部小学校 絵手紙教室 (PDF 265.8KB)

-
R7.10.10 黒石中学校 1年技術科(木工分野)補助ボランティア (PDF 183.7KB)

- 特色ある学校の取組(令和7年度)
- 特色ある学校の取組(令和6年度)
- 特色ある学校の取組(令和5年度)
- 特色ある学校の取組(藤山中学校の取組)
各学校のホームページ
各学校のホームページでは、
「地域学校協働活動」ページにて、コミスクの取組を紹介しています。
「学校だより」「学校の様子」ページにも、関係する記事が掲載されていますのでご覧ください。
ポータルサイトの下の方に、下の図のような各学校ホームページへのリンク一覧があります。

コミスクだより(宇部市のコミュニティ・スクール)
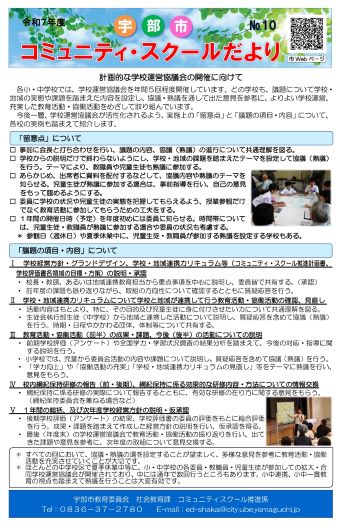
学校や地域に発信しているコミュニティ・スクールに関する情報紙です。
-
コミスクだより No.10 (計画的な学校運営協議会の開催に向けて) (PDF 252.9KB)

- コミスクだより(令和7年度)
- コミスクだより(令和6年度)
- コミスクだより(令和5年度)
- コミスクだより(令和4年度)
会議・研修
コミュニティ・スクールに関する会議・研修
宇部市コミュニティ・スクール推進協議会
教育委員会の施策の充実や各学校及び地域等の取組の改善に向けた協議を行います。
各中学校区の学校運営協議会の代表で構成されています。

第1回宇部市地域学校協働活動推進員連絡会議:5月27日(火曜日)

県主催の地域連携教育に関する研修会が統合・整理されたことや、宇部市社会教育委員会による提言書『「これからの宇部市の社会教育と私たちの地域づくり」について(令和7年2月)』が提出されたことなどを受けて、社会教育課では、今年度新たな会議を開催することとしました。その一つが、「第1回宇部市地域学校協働活動推進員連絡会議」です。この会議は、地域学校協働活動推進員を対象としたものですが、当日は推進員の推薦を担う、ふれあいセンター館長6名も参加しました。
会議ではまず、本課の社会教育主事による所管説明で推進員の役割を確認しました。推進員は「地域と学校をつなぐコーディネーター」の役割を担い、学校・地域の課題解決に必要な連絡調整や地域・学校の教育活動の企画や支援、その他関係団体等との連携調整といった活動をします。また、県・市が進める「大人の学び」について、実施に向けた共有を図りました。推進員は、単なる支援者、サポーター、ボランティアではなく、子どもたちの学びを支える学校のパートナーであることを再確認し、各自が認識を深めていきました。
会議の後半は、グループに分かれ、「(1)各校における地域学校協働活動の現状について」、「(2)児童生徒の意見を生かした地域学校協働活動の推進について」というテーマで情報交換を行いました。
事後のアンケートには、「情報交換はとても刺激的で勉強になりました。参考にしてできることに取り組んでみたいと思います」や、「学校との連絡を更に密にしていきたい」「もっと子どもたちと関わって思いを聞いていきたい」といった積極的な声がたくさんありました。
本会議が、学校と地域との協働活動の一層の充実に向けて、「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」の一体的な推進を図るきっかけとなるよう願っています。
第1回宇部市地域連携教育担当者連絡協議会:6月27日(金曜日)

山口県教育庁地域連携教育推進課と宇部市の地域連携教育担当者との連絡協議会が市役所庁舎で行われました。昨年度まで戦略会議と呼ばれていましたが、市町の地域連携教育の取組を県が伴走支援する形に改められました。
当日は、県から2名、宇部市からは学校教育課、市民活動課、宇部市校長会、社会教育課から13名、そして、アドバイザーとしてCSチーフ(県内6地区に配置された統括的なCS活動推進員)をお招きし、宇部市の重点取組事項の柱の1である「地域学校協働活動の推進」についてグループワークで熟議を行いました。
「地域貢献意識の向上」については、地域の多様な活動と学校が求めているもののマッチングが重要であることや、児童生徒の地域への愛着・愛情を育むには学校地域連携カリキュラムや大人の学び、総合的な学習の時間での探究的な学びを通して地域と関わり、行動につなげることが重要であることを確認しました。
また、「学校づくりと地域づくりの理解浸透」については、保護者世代の関わりや地域学校協働活動推進員の働きに注目し、子ども主体の活動を仕組むことが必要であることを確認しました。
令和6年度の国の調査では、宇部市の約8割の児童生徒が、「地域や社会をよくするために何かしてみたいと思う」と答えています。これが、「何かできる」さらには、「行動する」に変容し、地域の担い手として育ってくれるように、地域連携教育推進課とCSチーフからいただいた助言をもとに、これからも宇部市の地域連携教育を推進していきます。
第1回宇部市社会教育推進委員会連絡会議:7月2日(水曜日)

本会議は、宇部市福祉ふれあいセンターを会場とし、社会教育推進委員会会長及びふれあいセンター館長を対象に、社会教育推進委員会の役割や活動について理解を深めていただき、他地区との情報交換を行うことで、コミュニティ・スクールの取組と地域学校協働活動を一体的に推進することを目的として、今年度新たに実施したものです。
本課からの所管説明のあと、宇部フロンティア大学短期大学部の伊藤一統教授による講話「社会教育推進委員会の役割や活動について」を拝聴しました。具体的には、
「1.地域学校協働活動推進員を支援すること」
「2.現状を把握すること」
「3.社会教育推進のための計画を考え・推進すること」
「4.各所属や関係団体とつなぐこと」
「5.学びの事業を企画・運営すること」の5つをあげられ、それらの取組のポイントを一つ一つ分かりやすくアドバイスしていただきました。その後、グループごとに「社会教育推進委員会の活動事例や悩みごと」について、フリップディスカッションを行いました。参加者からは、地域の特色を生かした活動が展開されている他地区の様子を知ることができ参考になったという声が聞かれました。
今後もこういった学びや交流の機会を設けることとしており、社会教育推進委員会が、各地区の社会教育活動とともに地域学校協働活動を担う地域学校協働本部として、より一層の充実が図られることを期待しています。
10月7日(火曜日) 宇部市地域連携教育担当者研修会
地域連携教育を推進する関係者が一堂に会し、「学校運営協議会の一層の充実」や「地域学校協働活動の推進」について理解を深め、「地域とともにある学校づくり」と「学校を核とした地域づくり」の一体的な推進につながる体制づくりについて考えます。

ときわ湖水ホールにおいて、学校づくりと地域づくりの関係者が一堂に会する「地域連携教育担当者研修会」を、県教委と合同で(新たに)実施しました。
これは、昨年度まで実施していた「宇部市地域学校協働活動研修会」と、今年度新設した「宇部市地域学校協働活動推進員連絡会議」「宇部市社会教育推進委員会連絡会議」を兼ねて行ったものです。
前半は、4団体に各2回発表していただき、参加者はその中から2つを選んで聴講しました。内容は、
・船木地区社会教育推進委員会「船木地区社会教育推進委員会/R6年度活動実績」
・二俣瀬小学校学校運営協議会「小規模校を強みに変え、学校・地域の課題を解決する地域連携活動」
・恩田地区社会教育推進委員会「仲間とともに、子どもたちと楽しみ育ちあった、四半世紀を振り返る」
・厚南中学校学校運営協議会「生徒会を主体とした地域貢献活動」
の4つです。それぞれのブースでは、発表者の熱意あふれる発表内容を参加者が熱心に聴講し、質疑応答も行われました。
後半に行われたグループディスカッションでは、「未来へつなげよう!地域・社会のために私たちができること」をテーマに、どのグループも活発な情報交換や協議が進められ、会場が熱気に包まれました。
また、実施後のアンケートには、「5年先、10年先を見越した未来志向の体制構築に向けて多様な立場の方々と意見を交換しながら進めていきたい」「どの地区でも、高齢者と若い人(子ども)とのつながり、そして伝統を継承していくことが大切であると感じていた」「社教推の立場を明確にして、子どもと地域をつなぐ活動を考案していきたい」といった感想が寄せられていました。
これらの貴重な感想や意見を参考に、来年度に向けてさらに充実した研修会にしていきたいと思います。
第3回宇部市地域学校協働活動推進員連絡会議:1月20日(火曜日)

「第3回宇部市地域学校協働活動推進員連絡会議」が開催され、推進員22名とふれあいセンター館長2名が参加し、地域と学校の連携による教育活動の推進に向け、具体的な事例発表や情報交換が行われました。
まず、恩田地区の石川推進員から「三方よしの地域学校協働活動」と題した事例発表があり、近江商人の経営哲学「売り手よし、買い手よし、世間よし」にならい、地域学校協働活動を以下の「三方よし」として実践されている活動が紹介されました。
・役に立てて嬉しい子どもサポーター(売り手)
・見守ってくれて安心の子ども・学校(買い手)
・安心して子育てできる地域・保護者(世間)
子どもたちの成長を第一の喜びとする、恩田地区の熱意ある活動に、参加者は熱心に耳を傾けていました。
続いて、本市の社会教育主事から「他の地域に学ぶ」と題し、下関市、光市、長門市、下松市など他市町の事例が紹介されました。推進員に期待される役割として、「子どもたちが地域貢献する場の創出」「学校と関係機関の連携強化」「学校運営協議会の意見を地域につなぐ」といった具体的な活動例が示され、参加者は自身の活動を振り返る機会となりました。
会議の後半はグループワーク形式で、「各校における地域学校協働活動の今年度の取組」をテーマに活発な情報交換が行われ、「持続可能性」や「学校づくり・地域づくりへの発展」といった視点で意見を交わしながら、来年度の活動に向けた展望を共有しました。
終了後のアンケートでは、この情報交換が「今後の活動に大いに参考になった」との声が多数寄せられ、地域によっては失われつつある人々のつながりを意識し、「地域の一員として地域づくりに関わりたい」という熱い想いが共有され、推進員としての役割の重要性を改めて認識する、大変有意義な会議となりました。
関連情報
PDFファイルをご覧いただくには、「Adobe(R) Reader(R)」が必要です。お持ちでない方はアドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウ)からダウンロード(無料)してください。
このページに関するお問い合わせ
教育委員会事務局 社会教育課
〒755-8601 宇部市常盤町一丁目7番1号
- コミュニティ・スクールの推進、社会教育、社会教育委員会、社会教育関係団体の指導及び連絡調整、ユネスコ活動、家庭教育、宇宙教育の推進、放課後子ども教室に関すること
電話番号:0836-37-2780 ファクス番号:0836-22-6066
